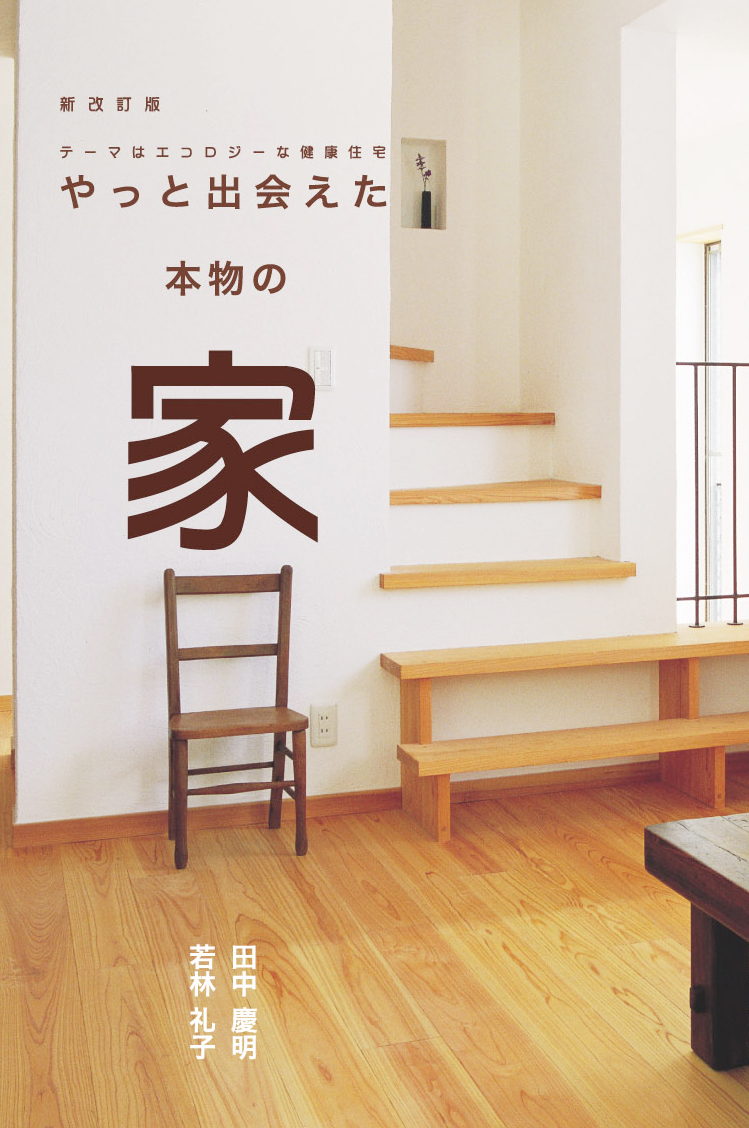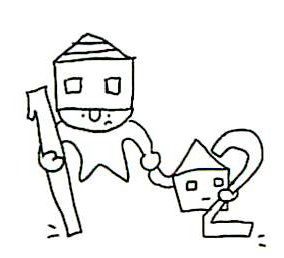第一章・8話|危険な美徳「もったいない」

建替えの時必ず言われることに「うちは物が多いから、収納をたっぷりとらないと」という言葉がある。一つの住まいに長く暮らせば暮らすほど増える物。
地方の広々とした土地に、それこそ蔵があるような住まいならまだしも、都心部の限られた土地、さらに厳しい建蔽率、容積率、加えて吉向さ制限、斜線制限だので、軒さえ思うに出せな い敷地条件の中でつくる住まい。
建替えの時に必ず今よりは少しでも広い家を、との要望は、どうやらこの年々増え続ける物 をいかにすっきり収納し、生活スペースを確保するかにあるようだ。まさに物とスペースとの 戦い。あるご主人日く「我が家のこの物たちは、ある日突然でなく、まるでインベーダーのご とく徐々に我が家を占領していった。」
その侵入者を野放図に招きいれてきた結果、子どもが出て行った後、子ども室は順番に納戸 と化しフル活用される。死に部屋になってるわけではないのだから良いではないかとの反論も あるかと思うが、住まいの中の物、これは本当に際限なく増えていく。
かつて物を大切にしていた時代は、使える物は使う、そしていかに棄てずに有効活用するか といったことが、物に対する基本精神だった。今のように、手入れする費用や手間などを考え ると買った方が安いといった物溢れの時代ではない。
しかしながら、物のなかった時代の、物に対する哲学がどこかで美徳とされ生き続けている。 その象徴的言葉が「もったいない」である。まずは食料。食べるものに困った経験を持つ世代 はそれこそ大変だ。賞味期限が切れようが、捨てようとでもするものなら「もったいない」「ば ちがあたる」とくる。特に保存食品的な缶詰類や乾燥食品、これは何年経っても食べられると 信じている。その賞味期限も、一度開封したら意味をなさないということなどおかまいなし。
そして冷蔵庫信仰とでもいおうか、冷蔵庫にさえ入れておけばよほどでないと腐らないと恩 い込んでいる。
台所用品も、あまりに手軽に買えるコストでちょっとあったら便利といった物が溢れている。 100円ショップなる存在は物溢れ時代を象徴している。
一、二回使って、収納の奥に仕舞い込まれ忘れ去られている物。また台所収納を占領するものの中には、心情的に棄てにくい物というのがある。使ってないセット物の小鉢や皿、カップ、 コップの類、漆器やお盆そして鍋などこれはほとんどいただき物。誰それさんの結婚式の引き 出物だの内祝いだので棄てるに忍びないということのようだ。
こうした物以外に増え続けるものが本と洋服ではないだろうか。さらにはやはりいただきも ののタオル類や寝具。もちろんかっての美徳を代表する、空箱やびん、包装紙、紙袋、紐やリ ボン、これもたまるとバカにならない。
さて、こうしたものたちに生活スペースを占領されないようにするにはどうしたら良いか、 少し具体的に考えてみたい。 まず、物に溢れた生活は、大変不経済であるということに気づいてほしい。スペースの無駄 だけではない。まず自分自身のことを考えてみれば、膨大なる時間をロスしていることになる。
いくら増えようとほったらかし、という生活であれば別だけれど、それだけ保有できる家は 少ないと思う。そうなれば、どこにしまうか一苦労し、場合によってはあちらに移しこちらに 移し、大掃除の時も大変だし、一大決心をして整理しようと思っても、結局はほとんど棄てら れない。ただただ時間と頭を悩ませただけ。食料品の賞味期限を一つひとつチェックしていく のもこれまた一苦労。
洋服などもクリーニングに出してあっても長期間扉のないオープンなクローゼットに掛けて おくと汚れる。着ないうちに、又、クリーニングというバカげたことにもなりかねない。
いつか着るかもしれないと棄てられないでたまっていく衣料品。どんなにスタンダードなス タイルのものでもやはり微妙に流行遅れとなってしまう。高いものだったからととっておいて ゆず もやっぱり宝の持ち腐れ。一一シーズン着なかった物は、誰かにあげる、譲る、最近はやりの古 着ショップにだすなどと決めると悩まずに整理ができる。
洋服に限らず、決められたスペース以上に物を増やさないと決心することも、かなり整理に 役立つ。例えば紙袋もこの箱に常に一箱ストックがあれば良い、食料品なども缶詰なら缶詰の ストックヤードを決めて、その中に収まる量だけと決めていく。 そしてもっと大切なことは、買う前に、本当に必要な物なのか?と自問してみることだろう。 物溢れの時代の次に間違いなくやってくるのが、ゴミの山であることは疑いのないことなのだ。
家を新しく建てる、それは今までの生活で積もり積もった物を思い切って整理する一大チャ ンス。20世紀後半誰しもが物ぶくれに悩んだ。新築をキッカケに大きく減量し、こころ豊か なシンプルライフといきたいものです。