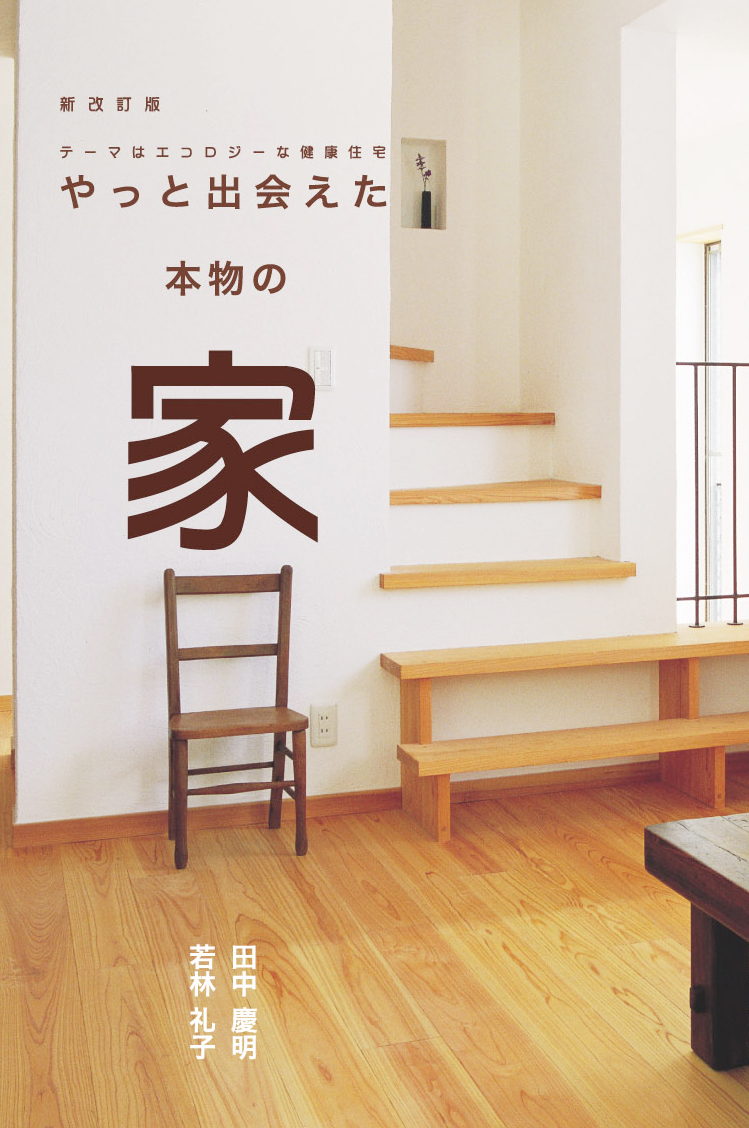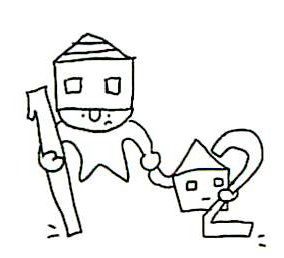第一章・11話|最期まで自立をめざす家づくり
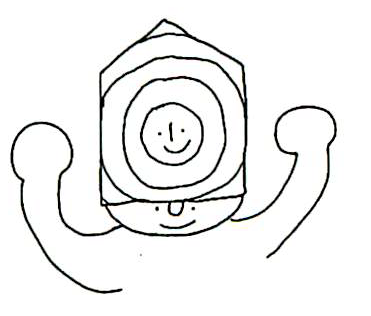
高齢者の一人ひとりが、最期まで自立をめざすこと、それがもっとも尊厳ある生き方であり、そうした高齢者の心身をサポートすることがバリアフリーの本来の目的ではないかと思っている。
今は元気な高齢者に、将来もし車椅子の生活になったらと事前に大掛かりな設備を導入するのはいかがなものだろう。自分のことは自分でできるように、ちょっとした環境を整えることの方が重要なのではないだろうか。
少しの不自由さであれば、何とかそこをカバーして自分で動けるように工夫する。それぞれの老化の程度や精神の強さは個人差が大きいのだから、それを一辺倒に考えるのは無理があると思う。
言うまでもなく、団塊の世代が高齢化する頃には、保険だの年金だのをあてにした生活設計は難しいのではないか。自分の生活は自分で守る、となればなおさら身体の健康を守ることと、 頭脳がきちんと働くようにしておかなければならない。普通の体力が保持されていれば、定年 後もまだまだ隠居生活は早過ぎるし、あまり早く社会から離れてしまうと男性などはかえって ぼけを促進しかねない。
問題は定年を迎えた後の社会的なつながりをどうつくっていくかということになる・自分の 特技、長年の仕事を通じて得意なことなどが生かせれば最高。趣味やボランティアの世界もあ る。やってて楽しいこと。金儲けとしてでなく、自分の生活が守れる程度であって良しとすれ ば、さわやかに生きれそうだ。
社会とのつながりは持ちながらも、金や物を目的とした世界からはできるだけ遠ざかれれば、 それだけ健康な生き方ができそうな気がする。
自分の身のまわりのことは自分でするんだと思っているか、将来は結局誰かの世話になるん だと考えるかで人生は大きく変わる。年寄り子どもなどと言って、年をとったら子どもと一緒 と、お年寄りのわがままを受け入れて暮らしている家族を見かけるが、これは大きな問題だと思う。
年寄り子どもという表現には、長い人生の経験を重ね、人間の持つさまざまな欲も浄化され、子どものように純粋なものの見方ができるようになった、聖人へ近づいた大人という意味がこめられていると思う。
あそこまで年齢がいってしまったら、いまさら何を言っても所詮変わらないし、反って可哀 想などという話を聞く。でもこうした扱いは、本人への思いやりには決してならないと思うし、 言っている人自身も同じような人生を送る結果となってしまうだろう。本人自身の意識レベル の問題と片付けないで、いい死に方をしてもらうためにも年寄り子どもと片付けてしまっては いけないと思う。
いい死に方ができるかどうかは、人生をどう生き切ったかで決まってくる。だからこそ、ど う人と関わりを持って生きてきたかが大きな要素となってくる。
家族何人と暮らしていても、子どもたちは出て行くもの、そして夫婦揃っていても、いつか は一人になるとの自覚を持って生きていかなくてはいけないと思う。独身であったり、結婚し ていても子どもがいなかったりすれば、必然的に将来の自分の生活を真剣にとらえざるを得ない。
子どもをこころの拠り所とするのは良いと思うけれど、最初から頼りにしたり、ちょっとで も当たり前との感覚を持つことは親として、いや人間として失格と言いたい。子どもや身内に 頼らないという姿勢が、結果として子どもを成長させることになり、また自立した生き方など ということを考えてもいなかったお年寄りへの良い刺激になると思う。
今では、自宅で自然死など望むべくもなくなっているが、身体だけでなく精神的にも死ぬま で健康であろうとすれば、誰かに頼った生き方、こころの持ち方をしていたら実現は遠のく一方と思う。
尊厳死、これは死ぬ瞬間のことでなく、死ぬ瞬間までいかにきちっとした生き方をしてきた かということに他ならない。残念ながら病院で死を迎えるようになってしまっても、その瞬間 が自分にとって今回の人生における成長の頂点でありたいと願っている。
ところで、一人暮らしの住まいづくりのお手伝いもさせていただいている。男性の場合も女 性の場合もあったけれど、いずれも、将来車椅子になった時のことを考えての設計は要求されなかった。
高齢者のためのケアつきマンションを将来の終の棲家とする方もある。また、都心部から離 れ、まさしく自然の中に身をおいて、自給自足に近い、これまでとは全く時間の流れ方の異な る世界へと飛び込んでいく高齢者も増えてきている。 どういう環境の中であっても、どういう暮らし方であっても、死ぬまで成長し続けられる生 き方が人としてこの世に生を受けたものの使命と思う。