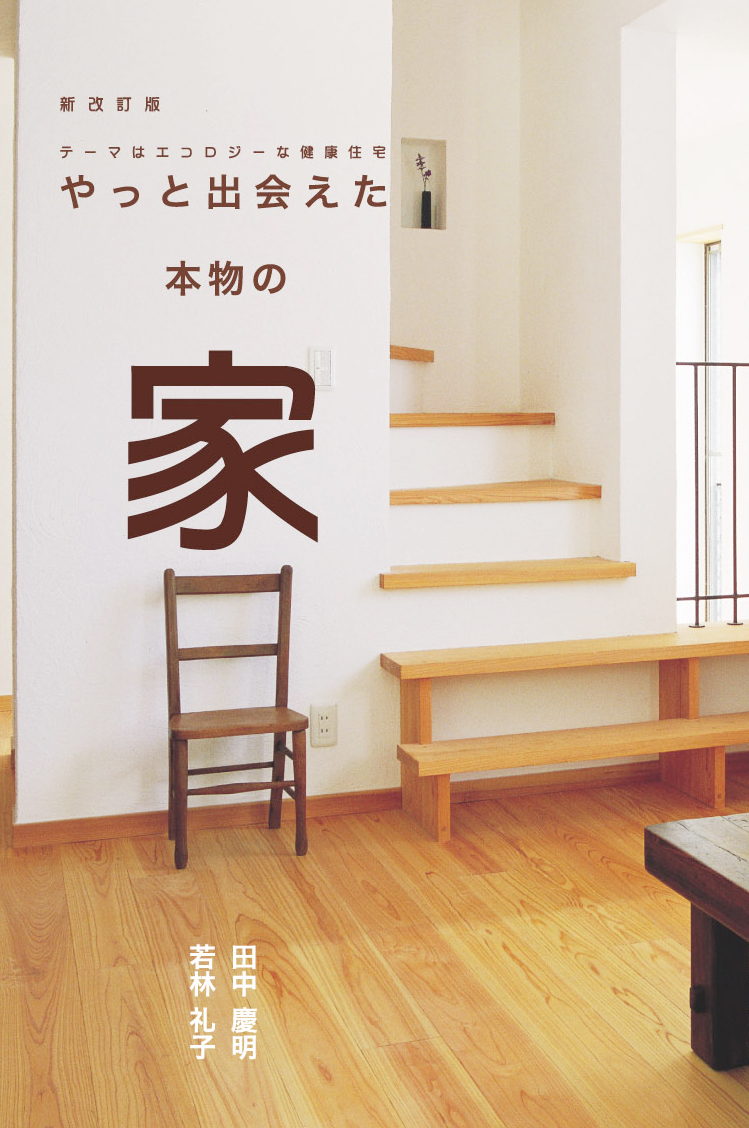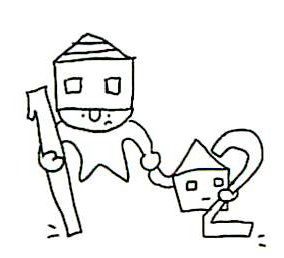第二章・11話|パッシブな家では外張り断熱は20年以上前から

断熱のジレンマは、ご理解いただけたと思います。この章では、断熱の方法論に触れます。
住宅の断熱方法は、大きく分けて二つになります。
一、充填断熱(内張り断熱とか内断熱とも言います)
二、外張り断熱(外断熱と言われることの方が多いようです。正確には外断熱はビル等に用 いられる用語なのですが)
充填断熱は、一般的にグラスウールを部屋のまわりに施工する方法です。壁の中に詰め込むので充填という用語が使われたのでしょう。
外張り断熱は、住宅の屋根・壁・基礎を外側からすっぽりと包み込む方法です。
現在の住宅建築においては、充填断熱が圧倒的で100%にせまるといっても過言ではありません。外張り断熱は、そういう意味ではゼロに等しいのです。
しかしここ数年、外張り断熱論議が巷をにぎわせています。その際ほとんどが、外断熱と表現されています。本来であれば、住宅に使用される用語ではなくまぎらわしいのですが、おそらくこの勢いでは、外断熱という用語は、住宅にも適用されてしまうのではと思います。
現在の住宅建築においてはゼロにも等しい外張り断熱が、何故ここまで話題になるのでしょうか。
その理由は簡単です。圧倒的独占状態にあるグラスウールによる充填断熱が、あまりにも欠陥的方法であるからです。ようやく、ほんの一部と言えども、それが専門家ではない、住宅建築を希望している一般の方に知られるようになってきたからです。
筆者も20数年にわたって、充填断熱の問題点を講演会や著書などで指摘し続けてきました。 本心から、全くの欠陥工法であると確信しています。
そのことは、グラスウールメーヵーや住宅業界そして国土交通省なども、十分に承知していることだと思います。それにもかかわらず、ここまで独占状態になってしまうと、眼に見える被害が続々と表面に現われ、マスコミに毎日のように取り上げられる、という状況にならないと、変えられない、見て見ぬふりを続ける、日本的なれあい状態になっています。
充填断熱の被害は眼に見えにくいのです。建物の見えない所で発生していますから。壁の中 で、床下空間で、そして天井裏の空間で、と。さらに、被害は建築後すぐに発生するだけではなく、2,3年後に、それに気づくのに10年かかったなんて具合です。
そして、その原因が充填断熱にあると特定できるとは限りません。最近、ようやく充填断熱の欠陥が表に出てきたのですから、これまでは、原因もわからないまま泣き寝入りしている人が大多数だというのが実態だったのです。
にもかかわらず、その大欠陥を抱えながら、住宅は一層の高断熱そして高気密をめざしています。ゾッとするばかりです。
本来であれば、充填断熱は禁止して外張り断熱にすべきなのですが、充填断熱の圧倒的独占状態を考えると、現代日本の社会機構では不可能に近いことでしょう。
そこで充填断熱をベースにして、何とか欠陥を少しでも取り除こうと、国土交通省の旗振りのもと、断熱方法の講習会やら湿気抜きの通気層そしてベーパーバリァなど、いろいろと苦心の跡が建築の基準にもおり込まれるようになりました。しかし、所詮は小手先の対処法にしか 過ぎません。
おそらく、この先10年、20年、日本の住宅は、対処困難な大欠陥を抱えた時限爆弾的存在になってしまうのでしょう。今現在、トピックスになっている化学物質問題以上の目に見えない爆弾かもしれません。これまでは、10,20年先のことなんてどうでもいい、むしろ早く腐ってくれた方が、建替え需要が増えて幸いだと公言されていたのですから。
私たちの提案しているパッシブな家では、20年以上も前から外張り断熱を実施しています。はっきりと言ってしまえば、その時点でも、住宅業界内部では充填断熱の欠陥はわかりきったことでした。
本来であれば、半数以上の建物が外張り断熱にされて当たり前、と思われる時間が経過したのですが、ゼロに近い状態から抜け出せていません。私たちの無力さと同時に、時代が、いまだ経済中心なのだとガッカリさせられます。これからは、せめて外張り断熱の方法が加速してほしいと願ってやみません。
しかし、すでに何度も強調していますが、外張り断熱にしてもそれだけで安全で健康な家ができるわけではないのです。
充填断熱の企業エゴ的独占状況も恐ろしいのですが、、外張り断熱を万能の神のように扱う危険性も同時に感じています。その裏にやはり、違う企業エゴが潜んでいるのが見えるようです。
健全な外張り断熱の発展のためには、健康な家づくりの実現において外張り断熱は、トータルな建築的手法のほんの一つでしかないと、落ち着いて自覚したほうがいいいのではないで しょうか。